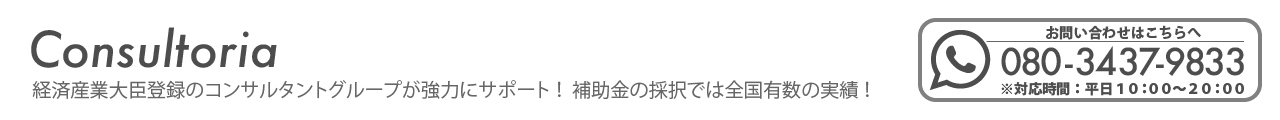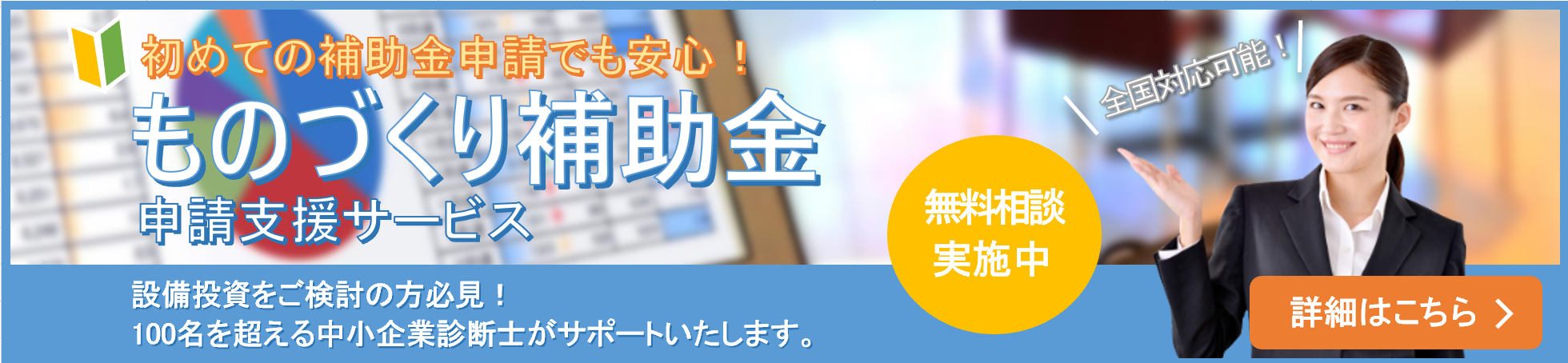昨今「経営者保証」が話題になっています。
経営者保証とは、株式会社などの法人が融資を受ける場合に、代表者個人が保証人になることを指します。
経営者保証により、万がいち倒産する等で返済できなくなった場合に金融機関は経営者個人に対して支払いを請求することができます。
しかし、経営者にとっては、保証人になっていると何かと負担感があります。
本メルマガでは、中小企業が経営者保証を金融機関に外してもらうためにどんなことを行うべきかのポイントを解説します。

1.経営者保証は金融機関の常識
2.経営者保証を外すために必要なこと
3.経営者は金融機関に依頼することが不可欠
4.信用保証協会の保証付き融資の留意点
5.最後に
これまで金融機関には「中小企業である法人へ融資する場合には経営者保証を条件とするのが当たり前」という認識がありました。
その背景には、金融機関の常識として以下2つの考え方があります。
①放漫経営への懸念
「経営者が保証人になっていないと、経営への責任感が欠如する」と金融機関は懸念しています。
②個人資産からの債権回収
金融機関は、法人が返済不能になった場合の債権保全の方策として、「代表者個人に請求する」または「個人資産を差し押さえる」といった
手段を確保する必要があります。そのために代表者を保証人にするべきであると金融機関は考えています。
しかし、筆者は日本政策金融公庫で融資の審査を担当していたことがあり、
その時の経験から「経営者保証無しの融資でも大きな問題は起こらない」と考えています。
日本政策金融公庫の「創業融資」や「マル経融資」も、融資先が法人の場合は経営者保証を不要としていますが、
放漫経営や責任感の欠如が見られた事例はきわめて限定的でした。
たしかに、債権保全の観点から考えると、経営者保証がある方が返済不能に陥った場合における債権回収の可能性は高まります。
しかし実際は、法人が返済不能に陥った場合には、経営者個人も経済的に破綻しているケースが大半でした。
以上のことから、経営者保証にはそれほど大きな意義はないと考えています。
また、経営者保証には、以下の3つの弊害があります。
①積極的な事業展開がしにくい
経営者は保証人になっていると、自身が破産するリスクを懸念して、積極的に融資を受けて事業展開しようという意欲が低下します。
②事業承継が難しくなる
後継者に事業を承継するとしても、経営者保証が残っていると、引退した経営者に個人保証がついて回ります。
さらには、金融機関が新社長へ経営者保証を引き継ぐよう求めると、「こんな大きな借金の保証人にはなりたくない」と言って、
承継自体を拒否することも起こり得ます。
③経営者の再起を阻害する
法人が倒産して経営者個人に債務の履行が求められ、経営者本人も破産してしまうと、新たなチャレンジが難しくなります。
以上のような背景を踏まえると、中小企業が金融機関と交渉し、経営者保証を外すことで、より思い切った経営が可能となります。
2013年に日本商工会議所と全国銀行協会が中心となり「経営者保証ガイドライン」が策定されました。
策定の目的は、「経営者保証による負担やリスクを解消して、中小企業の思い切った事業展開や早期の事業再生を後押しし、
ひいては日本経済を活性化すること」とされています。
中小企業が経営者保証を外してもらうためには、「経営者保証ガイドライン」の趣旨を踏まえ、金融機関に働きかけることが不可欠です。
「経営者保証ガイドライン」には保証人無しの融資を実現するための3つの要件が記載されており、中小企業が経営者保証を外してもらうためには、
この3要件を満たす努力が求められます。
①資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている
②財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である
③金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている
中小企業がこの3要件の全てを満たすことは、相応に高いハードルであると思われます。
しかし、経営者保証ガイドラインは、3要件の一部を満たせば、「すでに提供している経営者保証を見直すことができる可能性がある」としています。
重要なことは、決算書において①②の要件を満たしているように示すことです。
ここ数年来、金融庁が金融機関に対して、経営者保証無しでの融資を強く求めるようになりました。
以前よりも、経営者保証を外してやすくなっていると言えます。
経営者保証を外すには、積極的に金融機関へ依頼することが不可欠です。
ここでは、各場面においてどのように交渉すれば良いか解説します。
①創業融資を利用する
創業融資には、経営者保証無しとする制度が増えました。
日本政策金融公庫の場合、創業前から税務申告を2期終えるまでは、原則として経営者保証が不要です。
都道府県や市区町村の「制度融資」では、信用保証協会の「スタートアップ創出促進保証制度」ができたため、創業後5年以内の事業者は
経営者保証無しで利用できる可能性があります。
②既存借入の保証を外したい
すでに借りている融資の保証を外すことは容易ではありませんが、「5年後に事業承継を考えている」などの理由があれば、交渉により実現できる
可能性はあります。
③新規に借入をする
新規に借入をする場合は、経営者保証無しの融資を実現させるチャンスです。
金融機関側は、経営者保証を求めてくることが多いのが実態ですが、経営者保証ガイドラインを踏まえ、諦めずに交渉しましょう。
④事業承継を控えている
事業承継を目前に控えている場合は、融資を受けている金融機関へ説明し、経営者保証を外す交渉をしましょう。
また、既存借入については、後継者に個人保証を求められることもあります。
個人保証が条件となると、後継者が事業承継に意欲を失いかねません。
事業承継については、金融庁は金融機関へ強く指導している面もあるので、しっかり交渉することで経営者保証を外せる可能性が高い場面です。
⑤経営破綻してしまう
これは意外かもしれませんが、会社が倒産する場面でも、経営者保証を外せる可能性があります。
従来は法人が破綻したら、個人も破産せざるを得ないことが多くありました。
しかし、個人保証を外してもらうことで、個人の破産を回避し、再起できる可能性が高まります。
「経営者保証ガイドライン」には、以下の要件を満たす場合に保証人から保証債務の免除要請があった際は、
債権者である金融機関は誠実に対応すべきと定められています。
○法人(主債務者)が法的整理(破産・民事再生等)や私的整理及び、これに準じる手続(準則型私的整理手続)を開始申立済みであること
○主債務者の弁済計画等が債権者にとっても経済合理性が認められること
○法人(主債務者)及び保証人が弁済について誠実であり、債権者の請求に応じ、財産状況等について適時適切に開示していること
特に「経済合理性」が重要です。
例えば「自己破産すると返済できる資産がほとんどないので、自己破産せず払える範囲で払います」と説明することで、
金融機関の理解を得られることがあります。
筆者のとあるクライアントは、経営する会社が破綻した際に、
1億円の保証債務がありましたが、個人で200万円を支払うことで、保証を外してもらうことができました。
信用保証協会の保証付きで民間金融機関から融資を受けている場合の留意点についても説明します。
信用保証協会も、経営者保証無しの保証に注力するようになりましたが、筆者の印象ではややハードルが高いのが実態です。
各信用保証協会独自の基準が、それぞれの信用保証協会のホームページに記載されています。
(例)東京信用保証協会
(https://www.cgc-tokyo.or.jp/institution/guideline_2024/index.html)
新規に保証付き融資を受ける際など、取引金融機関と交渉することで、「経営者保証無し」の融資を実現できる可能性があります。
昨今、経営者保証を外すことについての実現可能性が高まっています。
そのためには、上記のような知識をもって金融機関と交渉することが不可欠です。
しかし、中小企業の経営者が独自で交渉しても、金融機関が動かないことがあります。
その際は、詳しい専門家へ相談・依頼することをお勧めします。
コンサルティング・ビジネス研究会 上野 光夫 (中小企業診断士)
—–