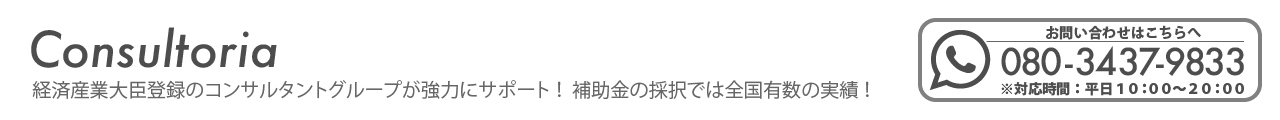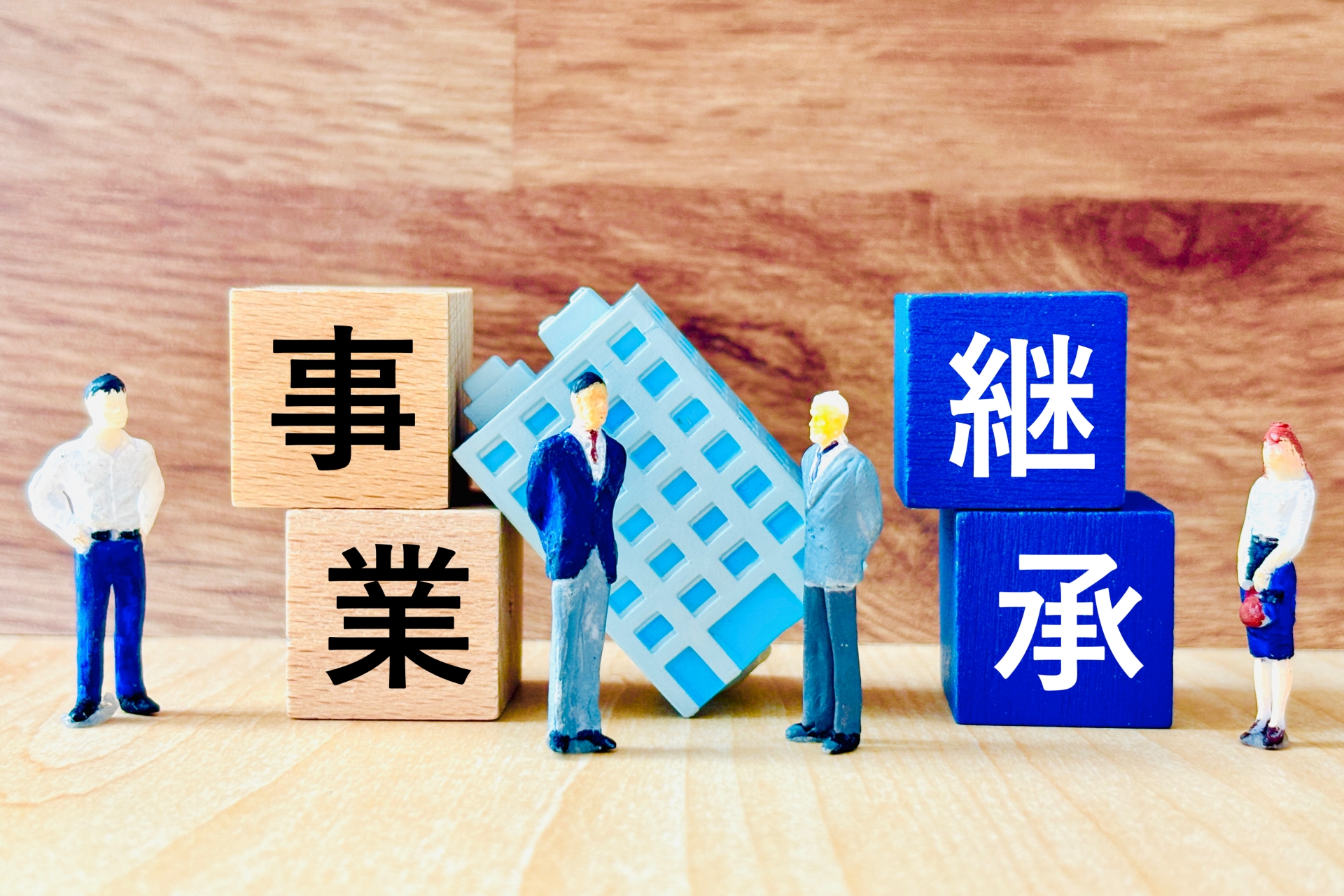
M&Aを「自力」でやろうとしていませんか?
M&Aには、専門家の知見が不可欠です。
「事業承継・M&A補助金」の専門家活用枠は、まさにその専門家費用を国が支援することで、皆様のM&Aを強力に後押しするための制度です。
| 目次 |
| 1.M&Aを「自力」でやろうとしていませんか?
2.専門家活用枠の二つの類型と補助上限額 3.補助の対象となる「専門家費用」とは? 4.失敗しないための申請ポイント 5.まとめ |
経営者の皆様、後継者問題や事業拡大のためのM&A(合併・買収)は、今日の経営戦略において非常に重要な選択肢となっています。しかし、「M&Aは費用が高くつく」「手続きが複雑で何から手をつけていいか分からない」と感じ、専門家の活用をためらっている方も多いのではないでしょうか。
M&Aは、法務、税務、財務、労務など多岐にわたる専門知識を要する一大プロジェクトです。ここで費用を惜しむと、後々のトラブルや思わぬリスクにつながりかねません。
「事業承継・M&A補助金」の専門家活用枠は、まさにその専門家費用を国が支援することで、皆様のM&Aを強力に後押しするための制度です。

この補助金は、M&Aのフェーズに応じて、以下の2つの類型が用意されています。
- 買い手支援類型(Ⅰ型): 事業を「譲り受ける」側を支援
- 売り手支援類型(Ⅱ型): 事業を「譲り渡す」側を支援
補助上限額と補助率
| 類型 | 補助率 | 基本補助上限額 | DD費用上乗せ | 廃業費用上乗せ |
| 買い手支援 | 2/3以内 | 600万円 | +200万円 | +150万円 |
| 売り手支援 | 1/2または2/3以内 | 600万円 | なし | +150万円 |
特に売り手支援類型では、直近決算期が赤字であるなど、一定の要件を満たすことで補助率が2/3に優遇されます。これは、困難な状況にある事業の存続を国が重視しているためです。
この補助枠の最大の魅力は、M&Aプロセスで必須となる高額な費用がカバーされる点です。
- FA(ファイナンシャルアドバイザー)・M&A仲介費用:
- 相談料、着手金、中間報酬、成功報酬など、M&Aの成立に向けた総合的な支援にかかる費用が対象です。
- 【重要】 補助の対象となるのは、「M&A支援機関登録制度」に登録された専門家のサービスに限られます。
- デュー・ディリジェンス(DD)費用:
- 弁護士、会計士などによる、財務・法務・税務などの詳細調査費用です。買い手支援類型では、このDD費用に対して最大200万円の上乗せ補助があります。これは、DDの徹底がM&A成功の鍵と認識されているためです。
- その他専門家費用:
- 最終契約書の作成・レビューにかかる弁護士費用、企業価値算定費用、不動産鑑定費用、各種登記費用などが含まれます。
- 廃業費用:
売り手支援類型を中心に、M&Aと併せて行う既存事業の廃業に伴う解体費、在庫廃棄費などが補助対象となります。
本補助金を確実に活用するためには、以下の点を厳守してください。
- 実質的な事業承継であること:単なる不動産や物品の売買、あるいは親族内承継などは対象外です。経営資源(設備、従業員、顧客など)の有機的な一体としての引継ぎが求められます。
- M&A支援機関の登録確認:利用予定のFA・仲介業者が「M&A支援機関登録制度」に登録されていることを必ず確認してください。
- フライングスタートの厳禁:補助事業は、「交付決定」の通知を受けてから契約・発注・支払いを開始しなければなりません。採択決定後であっても、交付決定前の契約は補助対象外(フライングスタート)となりますので、スケジュール管理を徹底してください。
相見積の取得:原則、50万円以上の専門家費用については、2者以上から相見積を取得し、最低価格の専門家を選定する必要があります(一部例外規定あり)。
事業承継・M&Aは、会社の未来、従業員の未来、そして地域経済の未来を左右する重要な決断です。この補助金を活用し、優秀な専門家の力を借りて、安全かつ確実にM&Aを成功させましょう。
まずは、お近くの専門家や事業承継・引継ぎ支援センターにご相談ください。
リンク:Consultoria 事業承継・M&A補助金 案内ページ
コンサルティング・ビジネス研究会 鈴木 貴仁(中小企業診断士)
——-