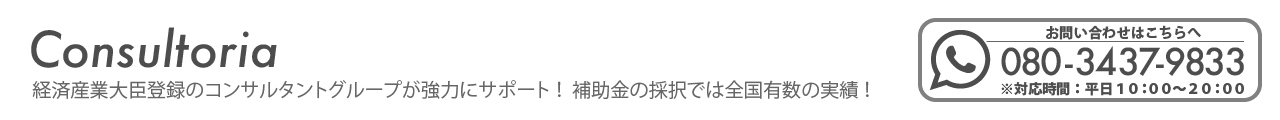中小企業の設備投資に向けた補助金としては、これまで「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」等が多く利用されてきました。しかし、ものづくり補助金は現在(7月26日時点)公募されておらず、事業再構築補助金は今後の公募がないと推測されています。
こうした状況のもと、企業の設備投資を支援する制度として注目を集めているのが、厚生労働省の「業務改善助成金」です。
今回は、本助成金のポイントをわかりやすくご説明します。さらに、労働者の所得水準向上のため、毎年秋に行われる最低賃金引上げに備え、本助成金を活用したうえで、9月までの賃上げ実施をお勧めいたします。

| 目次 |
| 1.業務改善助成金の概要
2.秋の賃上げに備えた本助成金の活用 3.業務改善助成金の特徴 4.本助成金の手続とスケジュール 5.まとめ |
1)業務改善助成金とは
業務改善助成金(以下、本助成金という)とは、事業場内最低賃金(職場内の従業員で最も低い時給)を引上げ、生産性向上に向けた取組み(設備投資等)を行った事業者に対し、設備などの費用の一部を助成する制度です。制度概要は下表の通りです。
※1 https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html を参照。
※2 労働保険の滞納がないこと、一定期間内に賃下げや解雇がないこと等。
これらに加え、以下の3点を盛り込んだ「事業実施計画書」を作成し、申請する必要があります。
①事業場内最低賃金を、30円以上引上げること
②引上げ後事業場内最低賃金を、就業規則等に明記すること
③生産性向上につながる取組み(設備投資等)を行い、費用を支出すること
2)「生産性向上に役立つ取組み」と活用事例
「生産性向上に資する取組み」としては以下のようなものがあります。
本助成金の活用事例は、厚生労働省「生産性向上のヒント集」(以下URL)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001123285.pdf
3)助成率
本助成金の助成率は、事業場内最低賃金によって変わります(以下を参照)。なお、決算書類に基づく労働生産性が3年前と比較して一定率程度伸びているという要件(生産性要件)に該当すると助成率があがります。
※1 生産性要件を満たす場合は、助成率が10分の9になります。
※2 生産性要件を満たす場合は、助成率が5分の4になります。
4)上限額
助成上限額は、賃金を引上げる労働者の数と、賃上げ幅に基づく4つのコース区分で決まります(下表を参照)。
1)最低賃金は近年大きく引上げられている
この10年の最低賃金(全国加重平均)は、コロナ禍の2020年を除き、2016年以降は毎年25円以上が引上げられており、特に2022年・2023年は30円以上の大幅な引上げとなりました。賃上げの推進が国の重要な政策であることや、物価高騰等を考慮すると、2024年も30円以上の最低賃金引上げが見込まれます。
<参考> 東京都における賃上げの例
(例)パート等の従業員10人・時給1,113円・労働時間1,500時間の会社が最低賃金30円引上げに対応して時給を30円引き上げる場合
本助成金を活用した設備投資等により、生産性を向上させることで賃上げに伴うコスト増のカバーにつながります。秋の賃上げに向け、今すぐにでも本助成金の活用をご検討ください。
2)秋の賃上げを機会に、設備を導入しよう!
本助成金を利用するためには、事業所内の最低賃金を引き上げる必要があります。秋の賃金引き上げ前に、最低賃金を引き上げ、本助成金を活用することをお勧めします。
本助成金には、ものづくり補助金などと比較して、次の3つの特徴があります。
1)申請手続きと審査が簡便
・業務改善助成金:事業実施計画書がシンプルで、審査基準も緩やか
・ものづくり補助金:10ページ程度の詳細な事業計画書が必要(採択率は約35.8%(第18次締切時点)と競争率が高い)
2)助成率が高水準
・業務改善助成金:助成率 75%~90%(4分の3から10分の9)
・ものづくり補助金:補助率 50%~66.7%(2分の1から3分の2)
仮に税抜400万円(税込440万円)の設備を導入する場合、自己負担額は下表になるため、業務改善助成金の方が有利です。
3)対象経費が多様
本助成金は、機械装置購入費のほか、セミナー受講料・マニュアル印刷費など、幅広い経費を申請できます。特に、物価高騰等により利益率が一定程度下がった事業者(特例事業者)は、補助金等では対象外の一部車両やパソコンも申請できるのは魅力です。
今回は、業務改善助成金のポイントと、秋の賃上げに向けた活用方法を説明してきました。
コンサルティング・ビジネス研究会には、厚生労働省の助成金の申請を支援できる社会保険労務士も在籍しております。ぜひともご相談ください。
コンサルティング・ビジネス研究会 多賀 俊二(中小企業診断士)
—–